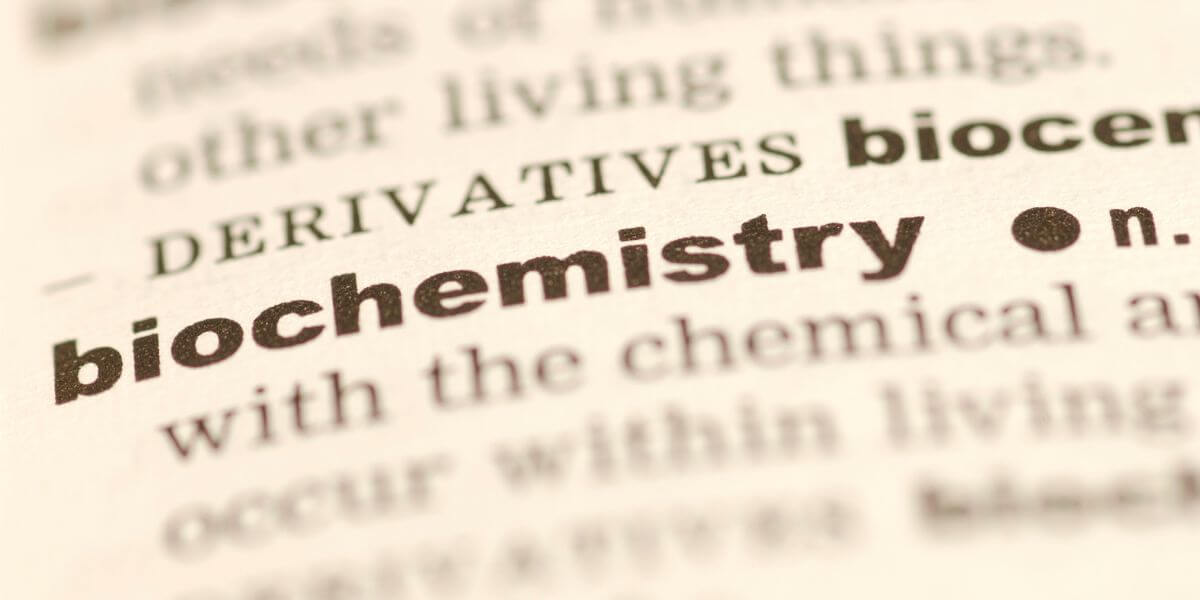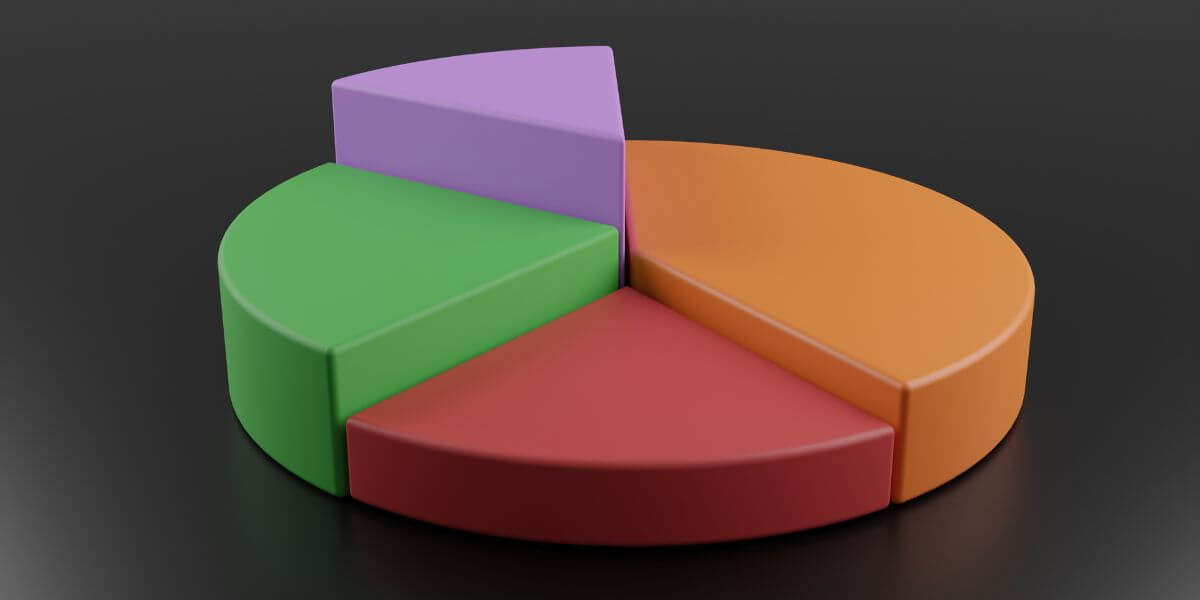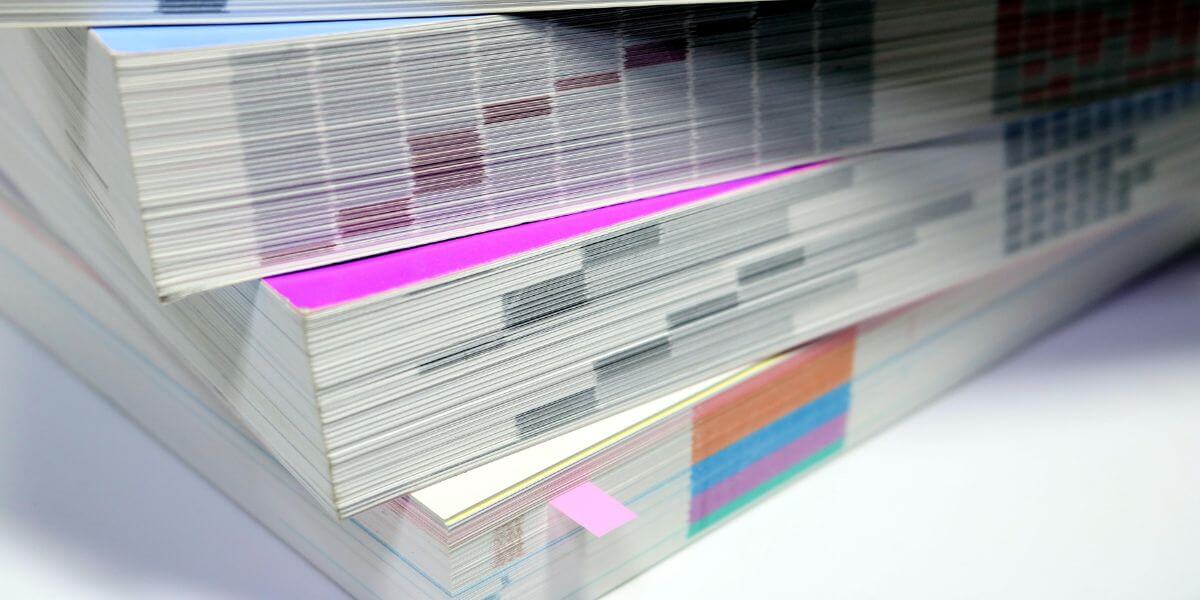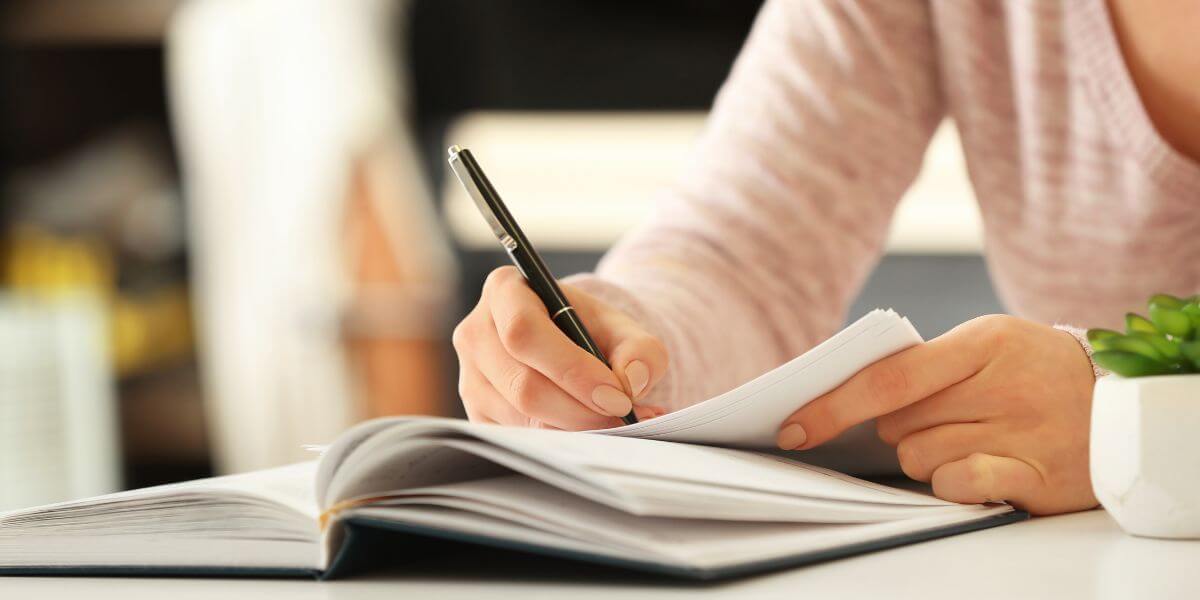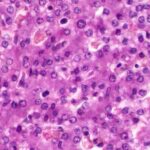【2025年版】医師国家試験勉強法|生化学を効率的に攻略する完全ガイド
医学部科目別進級対策シリーズ〜③ 生化学
医学部生の多くが苦手意識を持つ生化学。膨大な代謝経路の暗記に追われ、CBTや医師国家試験対策で躓く学生も少なくありません。しかし、適切な医師国家試験勉強法を身につければ、生化学は確実な得点源となります。
本記事では、医学部定期試験からCBT、そして国試対策まで一貫して使える効率的な生化学の学習法を、現役医学部生・医師国試受験生のために体系的に解説します。糖代謝・脂質代謝・アミノ酸代謝といった頻出分野の攻略法から、効果的な暗記のコツまで、医学部生の勉強法として実践的な内容をお届けします。
生化学(Biochemistry)とは – 医師国試勉強スケジュールの要
導入
生化学は、生命活動を代謝や酵素反応の側面から理解する学問となります。糖代謝・脂質代謝・アミノ酸代謝といったエネルギー産生の仕組み、DNAやRNAなどの核酸代謝、タンパク質合成など、細胞内部で起こる化学反応を体系的に学びます。医学部学生にとっては「目に見えない反応経路を丸暗記しなければならない」という印象が強く、苦手意識を持つ人も多い分野です。しかし、国試では糖尿病や脂質異常症、尿素回路異常など臨床疾患と直接関連した形で出題され、病態理解の基礎になります。臨床との接点を意識することで、「暗記科目」から「臨床を理解する武器」へと変わる重要な科目です。
生化学の全体像 – CBT・医師国家試験対策の基礎
全体像
生化学で扱うテーマは広大ですが、整理すると大まかに以下のような体系に分類できます。
糖代謝
解糖系、TCA回路、電子伝達系が主役となる範囲です。ATP産生の中心であり、生理学や解剖学で学ぶ臓器機能とリンクしながら理解することが重要です。糖尿病をはじめとする糖代謝疾患の理解には必須な知識となります。
脂質代謝
脂肪酸合成・分解、ケトン体生成、コレステロール代謝を扱います。臨床では動脈硬化、脂質異常症などCBT・国試の頻出範囲の理解に直結します。
アミノ酸・タンパク質代謝
尿素回路、必須アミノ酸と非必須アミノ酸、代謝異常症を学びます。アミノ酸代謝は特にフェニルケトン尿症やホモシスチン尿症など、小児の先天性代謝疾患を理解するのに重要で、CBT・国試頻出範囲となります。
核酸代謝
DNA・RNAの合成と分解などを扱います。プリン代謝異常(Lesch-Nyhan症候群、痛風)はCBT・国試において必ずおさえるべきテーマとなっています。また、メトトレキサートは葉酸代謝を阻害しDNA合成を抑制するため、白血病や関節リウマチの薬剤として使用されることも重要です。
酵素反応速度論
生化学の根幹原理として代謝経路の他に酵素反応速度論の学習が必須となります。CBTでは酵素反応速度論を直接問うような出題が多く、この理論は薬理学等の理解にも不可欠です。
ホルモンと細胞内シグナル伝達
インスリン・グルカゴン・甲状腺ホルモンの作用やそれに伴い細胞シグナルが細胞内でどのように伝達されるかを学びます。全般的なシグナル伝達を学ぶことでCBTでの生化学のカバーのみならず、抗がん剤の作用機序、自己免疫疾患、がん治療薬の機序を理解することが可能です。
これらを単に暗記するのではなく、「どの反応がどの疾患や薬物と関わるか」を意識すると効率的に学習が可能となります。
医師国家試験頻出ポイント – 効率的な国試対策
国試頻出ポイント
1. 糖代謝と糖尿病
解糖系・TCA回路・電子伝達系は基礎中の基礎ですが、国試では「糖尿病患者の代謝変化」がよく出題されます。インスリン不足で解糖系が低下し、脂肪酸分解とケトン体産生が亢進、代謝性アシドーシスに至る流れは頻出パターンです。
2. 脂質代謝と臨床疾患
コレステロール合成に関わるHMG-CoA還元酵素はスタチン系薬の標的となります。国試でも脂質代謝に関わる薬剤の機序に関する問題は頻出です。また、CBTでは飢餓時代謝に関連したケトン体利用、及びそれに関連する代謝経路も頻繁に出題されます。
3. 尿素回路と代謝異常症
オルニチントランスカルバミラーゼ欠損症など、小児科領域で「新生児の嘔吐・意識障害」として出題されます。尿素回路の関連疾患はCBT, 国試を通じて小児科範囲では押さえておくべき疾患群となります。
4. アミノ酸代謝異常
フェニルケトン尿症、ホモシスチン尿症はCBT領域において典型問題として出題されます。症例形式で「小児、発達遅滞+代謝異常」を示されることが多く、国試領域においては小児科とも強く結び付きます。
5. 酵素反応速度論
酵素反応速度論はCBT範囲においてミカエリス・メンテン式の知識を直接問う出題が多いです。国家試験では直接問うことは珍しいですが、薬理学の薬剤半減期等の問題に関連して出題されることがあります。また、抗菌薬の時間依存性、濃度依存性薬剤の理解にも寄与し、感染症領域の理解に役立ちます。
6. ホルモンと細胞内シグナル伝達
ホルモンのシグナル伝達方式(細胞膜受容体、核内受容体など)CBTでは頻出です。細胞のシグナル伝達はCBTでは暗記必須であり、国試領域でも頻繁に出題されます。特に国試範囲において抗がん剤や自己免疫疾患などの薬剤の作用機序を把握するのに絶対に必須の知識となります。
生化学の学習のコツ – 医学部生の勉強法
学習のコツ
生化学を攻略するには、丸暗記から脱却し「理解」と「関連付け」を重視することが大切です。生化学の反応、代謝経路は複雑であるため、経路は図で覚えるのが鉄則で、解糖系・TCA回路・電子伝達系を一枚の図にまとめれば流れを視覚的に把握できます。教科書等にも1枚ににまとまったスライドが添付されていることがあります。また、QBや過去問で問われ方を知ることも欠かせません。出題傾向を把握してから暗記すると効率が高まります。さらに生理学、薬理学などと関連付けた学習を意識するとよいでしょう。生理学と合わせればホルモン作用が理解しやすく、薬理学と結びつければ細胞内シグナル経路の理解が深まります。
まとめ – 生化学攻略で医師国家試験合格へ
まとめ
生化学は「膨大な代謝経路をひたすら暗記する科目」と思われがちですが、糖尿病・脂質異常症・尿素回路異常・痛風・がん・自己免疫疾患といった臨床疾患に直結するため、CBT・国試では必修かつ得点源となります。理解と臨床応用を意識することで、暗記負担は大幅に軽減されます。基礎を確実に固めれば、病態生理や薬理、内科の学習がスムーズになります。