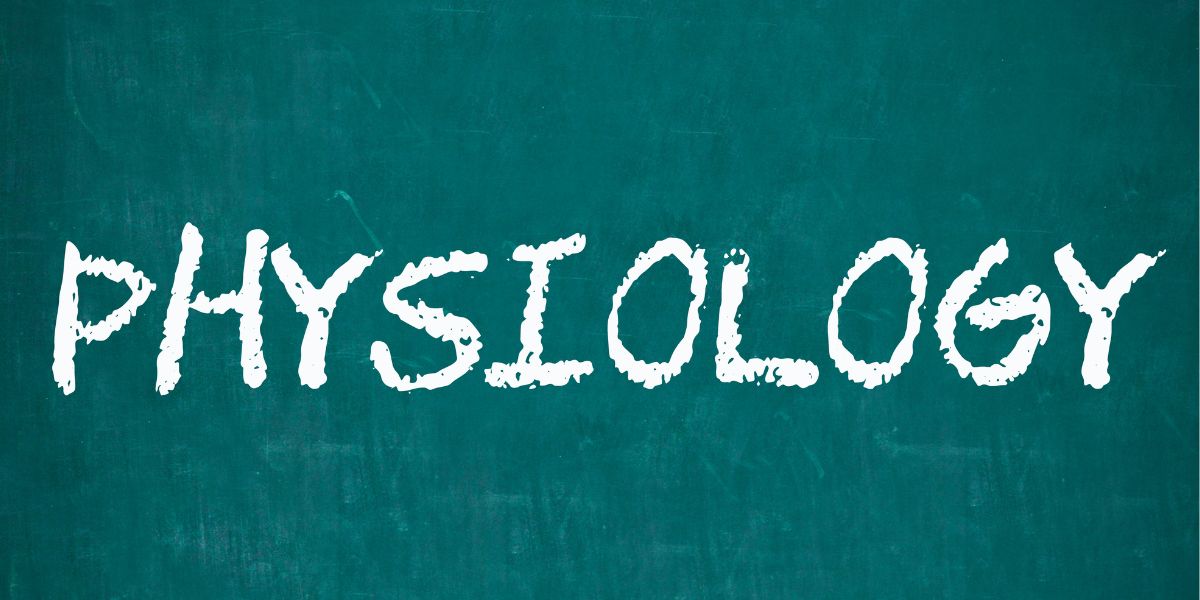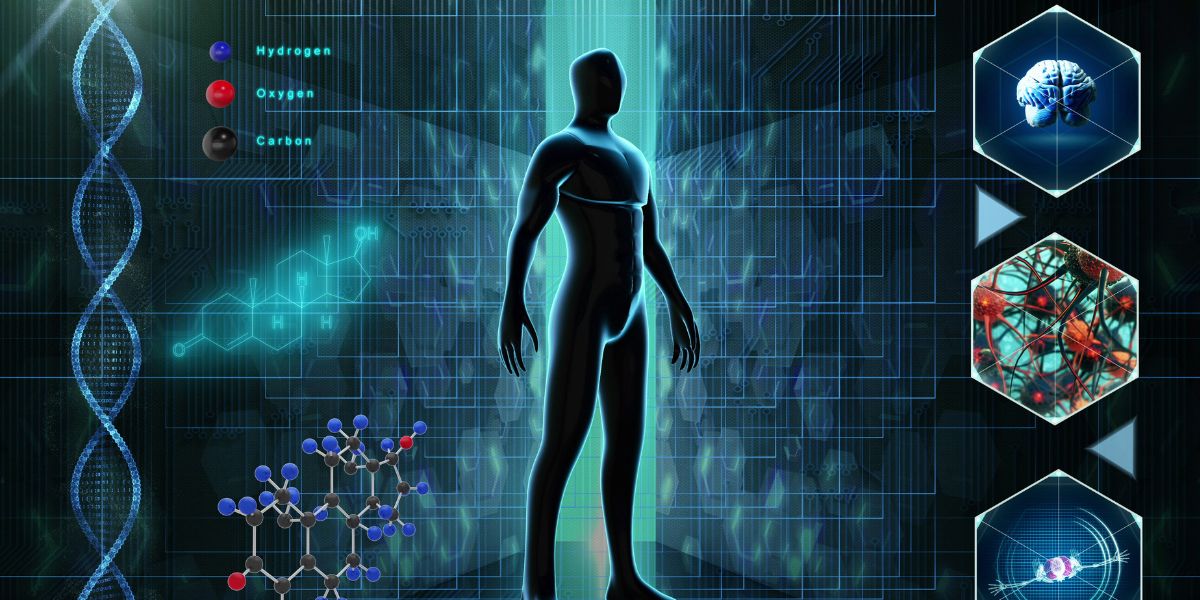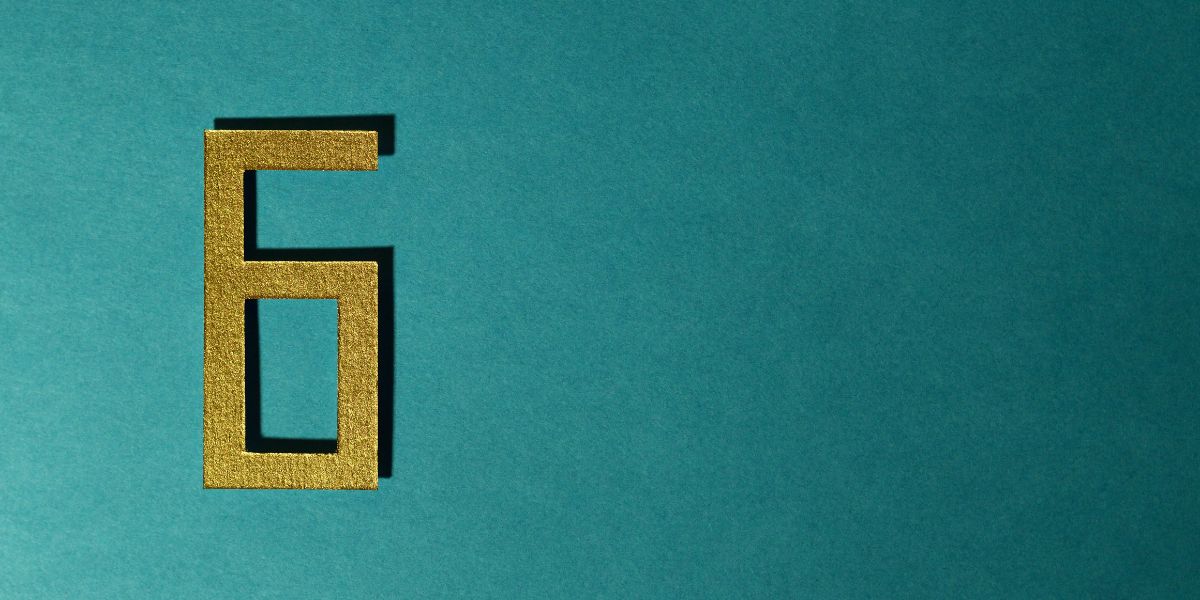【2025年版】医師国家試験勉強法|生理学を理解で攻略する完全ガイド
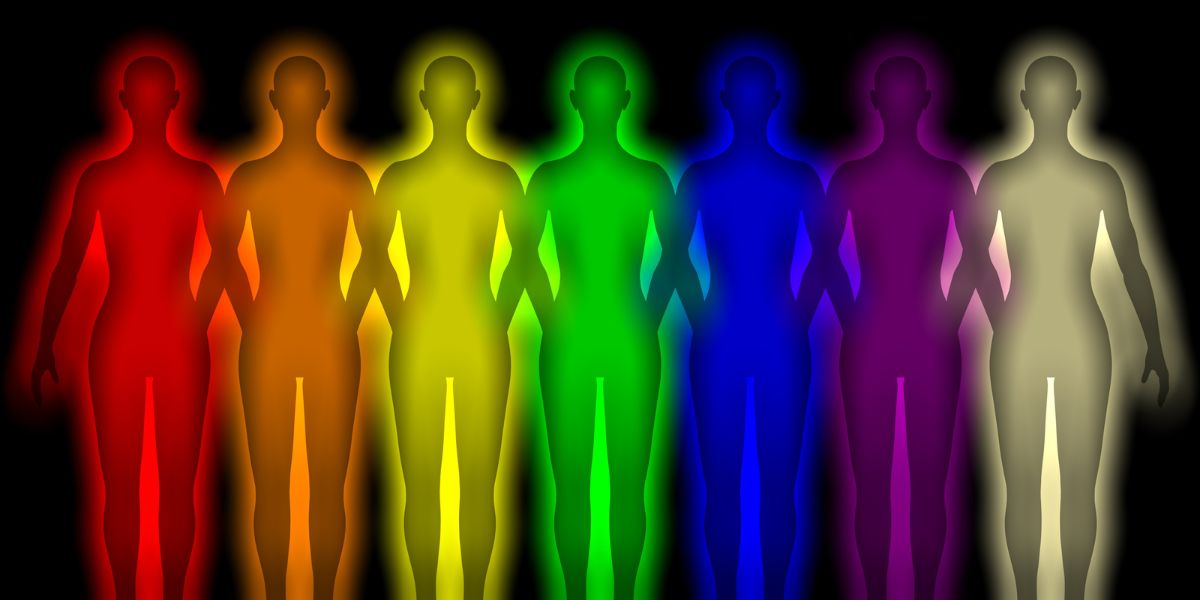
医学部科目別進級対策シリーズ〜④ 生理学
医学部の基礎医学の中核を成す生理学。暗記中心の他科目と異なり、「仕組みを理解すれば攻略できる」という特徴を持ちながら、範囲の膨大さから多くの医学部生が苦戦する科目です。しかし、適切な医師国家試験勉強法を身につければ、生理学は確実な得点源となります。
本記事では、医学部定期試験からCBT医学部試験、そして国試対策まで一貫して使える効率的な生理学の学習法を解説します。循環器・呼吸器・腎臓・神経系といった主要システムの理解から、フィードバック機構や活動電位などの重要概念まで、医学部生の勉強法として実践的な内容をお届けします。
生理学(Physiology)とは – 基礎医学から臨床への架け橋
導入
生理学は、解剖学で学んだ「構造」がどのように機能しているのかを理解する学問です。心臓の拍動、肺でのガス交換、腎臓での濾過と再吸収、神経の興奮伝導など、人体のあらゆる働きを定性的、定量的に説明することが目的です。暗記に偏りがちな解剖学や生化学に比べ、生理学は「仕組みを理解すれば理解が早い」という特徴があります。しかし、範囲が膨大で、循環・呼吸・腎・神経・消化・内分泌・血液と複数の系を並行して学ぶ必要があること、また数式やグラフを使った定量的説明が多いことから、多くの学生にとってハードルの高い科目でもあります。CBTでは生理学が幅広く出題され、国家試験を見据えると生理学の理解が臨床科目(循環器、呼吸器、腎臓、神経、内分泌)の理解と直結しているため、けっして蔑ろにできない分野となっています。
生理学の全体像 – 7大システムのCBT・国試対策
全体像
生理学は人体の機能を系統ごとに学びます。
循環生理
心臓の刺激伝導系、心拍出量、血圧調節を学びます。Frank-Starlingの法則や心電図の基礎を生理学から理解することで、不整脈や心不全の病態、治療に応用可能です。
呼吸生理
換気・拡散・灌流の仕組みや呼吸不全の分類やその病態について学びます。酸素解離曲線や肺活量曲線の理解は、呼吸不全や低酸素血症の病態理解に直結します。また、呼吸不全の分類や病態について学ぶことで臨床範囲での鑑別や治療法の深い理解に繋がります。
腎生理
糸球体濾過、尿細管再吸収・分泌、腎クリアランスを学びます。水電解質・酸塩基平衡を学ぶことで、臨床で遭遇する低Na血症・高K血症の鑑別や治療法の理解に直結します。また、利尿剤も様々な機序のものが存在し、その理解にも必要な知識となります。また、高血圧の病態に腎臓(副腎)が関与する腎性高血圧も存在し、その理解に生理学の関与が不可欠です。
神経生理
静止膜電位と活動電位、シナプス伝達、感覚・運動系について学びます。臨床では麻酔薬の作用機序やパーキンソン病など神経変性疾患の理解に不可欠です。
消化生理
胃酸分泌、胆汁分泌、膵酵素の働きを学びます。消化酵素の分泌機序や消化吸収の制御理解を理解することで臨床で用いられる下剤の作用機序や消化吸収の異常を主体とする疾患の理解に役立ちます。
内分泌生理
ホルモン分泌とフィードバック機構について学びます。視床下部-下垂体系、甲状腺、副腎の理解は国家試験でも必修レベルとなっています。特に内分泌内科の疾患において基本的な内分泌のフィードバック機構の理解が鑑別に必須です。また、近年出題が増加している糖尿病の薬剤機序についても理解を深めておきましょう。
血液生理
血液凝固、免疫機能、酸素運搬能について学びます。これらの知識は貧血や凝固異常の理解に欠かせません。特に国家試験の凝固異常では1次止血、2次止血の鑑別にあたり血液凝固機構の理解は必須の物となっています。
医師国家試験頻出ポイント – 6大重要テーマ
国試頻出ポイント
1
循環生理と血圧調節
心拍出量=一回拍出量×心拍数などは必修で毎年出題される公式です。特に心不全の治療において重要であるため、循環生理の整理をCBT・国試前に行いましょう。
2
呼吸生理とガス交換
酸素解離曲線の右方シフト(低pH・高CO₂・高温)は定番。呼吸不全の分類(Ⅰ型=PaO₂低下、Ⅱ型=PaCO₂上昇)も近年のCBT・国試で必ず聞かれる問題となっています。
3
腎生理とクリアランス
腎臓疾患では特に尿細管のどの部位が障害されているかを細かく理解することが必要となります。特に先述したように利尿薬の作用部位別に電解質がどのように推移するかの理解も求められます。
4
神経生理と活動電位
細胞の基本膜電位、脱分極、再分極の基礎を理解することで局所麻酔薬(Na⁺チャネル遮断)、全身麻酔薬の機序の違いをスムーズに理解できます。麻酔科領域では全身麻酔、局所麻酔に使用する薬剤の違いを明確に区別しましょう。てんかんや重症筋無力症など神経疾患の症例問題でも生理学の基礎知識が必要となります。
5
内分泌フィードバック
視床下部-下垂体系-標的臓器系のフィードバックに関する問題は毎年出題されます。Cushing症候群の鑑別(下垂体腺腫 vs 異所性ACTH産生腫瘍)や甲状腺機能亢進症のフィードバック抑制機構など、生理学の基礎知識は病態理解に直結します。
6
血液生理
酸素解離曲線やヘモグロビンの性質は貧血問題の基盤となります。凝固カスケードと抗凝固療法も国試の定番で、特に先天性凝固異常疾患についての問題としてCBT・国試で繰り返し出題されます。
生理学の学習のコツ – 理解重視の医学部生勉強法
学習のコツ
生理学は「丸暗記ではなく仕組みの理解」が鍵です。まず図とグラフを重視しましょう。Starling曲線、酸素解離曲線、クリアランス計算式などは視覚的に整理すると理解が深まります。「低酸素血症では解離曲線がどう動くか?」「出血性ショックで血圧はどう変化するか?」と考える癖をつければ基礎医学での知識が臨床問題にも応用可能になります。
さらに数式の意味を理解することも重要です。心拍出量や血圧の公式は単なる暗記ではなく、病態を説明するツールとなります。また、CBT, 国試の過去問を用いた演習も大切です。生理学は問われ方がパターン化されているため、CBT, 国試演習での学習効率が高い科目となっています。また、過去問を用いることで生理学での数式などのどのように使用するかの理解も深まります。
最後に落とし穴として、生理学は範囲が膨大であるために単なる用語暗記に終始することがあります。教科書を読むだけでは身につきにくいため、必ず臨床問題と結びつけて理解を深めるようにしましょう。
まとめ – 生理学マスターで臨床医学への扉を開く
まとめ
生理学は、人体の機能を体系的に理解する学問であり、循環・呼吸・腎・神経・内分泌といった臨床科目に直結します。暗記ではなく理解を重視することで、国試必修の得点源になるだけでなく、臨床の現場で「なぜそうなるのか」を説明できる力が身につきます。